Z世代にとって案件動画が当たり前という記事がありました。この記事では、クイックリサーチサービス「サークルアップ」が2025年4月に行った現役大学生への調査結果をもとに、Z世代が案件動画をどのように受け止めているか書いてあります。今回はこの記事を元に企業側からの視点で書いてみたいと思います。
https://sumaholife-plus.jp/sns/27207/
Z世代と呼ばれる若い層においては、インフルエンサーの影響力がますます高まっているように感じます。この調査によると彼らはSNS上でインフルエンサーが発信する「案件動画」が当たり前の存在となっていることがわかります。
企業側として、ただインフルエンサーに依頼すれば売れるという単純な話ではありません。Z世代は情報の真偽に敏感で、企業側の「やらせ感」や「押し付け感」をすぐに見抜きます。
なぜ今、Z世代向けインフルエンサーマーケティングが注目されるのか?
まず、なぜZ世代をターゲットとしたインフルエンサーマーケティングがこれほどまでに注目されているのでしょうか。その背景には、Z世代特有の消費行動と情報収集のスタイルがあります。
Z世代は、生まれた時からインターネットやSNSが身近にあるデジタルネイティブです。彼らはテレビや新聞といった従来のマスメディアよりも、YouTube、Instagram、TikTokなどのSNSから情報を得ることが多く、特に同世代や自分の趣味趣向に近いインフルエンサーの発言に関心と場合によっては絶大な信頼を寄せることがあります。
Z世代をターゲットとしている中小企業にとって、この世代の特性を理解し、彼らに響く形でアプローチすることは、将来の顧客獲得において非常に重要です。インフルエンサーマーケティングの特徴として
- 比較的低コストで始めやすいケースがあること
- 特定の趣味嗜好を持つニッチなターゲット層にも的確に情報を届けられること
- 共感や信頼をベースにした情報発信により、高いエンゲージメントが期待できること
などのメリットがあり、大企業だけでなく中小企業にとっても有効なマーケティング戦略となりえます。
Z世代は案件動画をどう見ている?リアルな調査結果を公開
それでは、実際にZ世代はインフルエンサーの「案件動画」をどのように見ているのでしょうか。「サークルアップ」の調査結果から、その実態を探っていきましょう。
案件動画は当たり前?Z世代がよく見るジャンルとは
調査によると、Z世代にとって案件動画は非常に身近な存在であることがわかります。実際に見たことがある案件動画のジャンルを尋ねたところ、「よく見る」「たまに見る」と回答した割合は以下の通りでした。
- コスメ: 75%
- スキンケア: 70%
- 食品: 57%
- 脱毛、歯列矯正、美容施術、整形など: 55%
- 衣服: 52%
実に5項目で半数以上が「案件動画を見たことがある」と回答しており、特にコスメやスキンケアといった美容関連のジャンルでは非常に高い視聴経験率を示しています。これは、商品の使用感や効果が視覚的に伝わりやすい動画コンテンツと親和性が高いジャンルであること、また、Z世代の関心が高い分野であることが影響していると考えられます。
中小企業経営者の皆様も、自社の商品やサービスがこれらのジャンル、あるいは動画で魅力を伝えやすいものであれば、インフルエンサーマーケティングとの相性が良いと言えるかもしれません。
案件動画=購入ではない?シビアなZ世代の購買行動
では、案件動画を見たZ世代は、実際に商品やサービスを購入しているのでしょうか。調査結果は、ジャンルによって購入率にばらつきがあることを示しています。
「案件動画を見たことがある」と回答した層のうち、「購入したことがある」と答えた割合は以下の通りです。
- コスメ: 30%
- スキンケア: 24%
- 食品: 23%
- 衣服: 23%
- 脱毛、歯列矯正、美容施術、整形など: わずか4%
コスメやスキンケア、食品、衣服といった比較的低価格帯の商品は、視聴経験者のうち半数弱が購入経験があると回答しており、案件動画が一定の購買促進効果を持っていることが伺えます。
一方で、「脱毛、歯列矯正、美容施術、整形など」といった高額なサービスに関しては、購入経験者はわずか4%にとどまりました。これらのサービスは金額が大きく、意思決定に慎重さが求められるため、動画を一度見ただけでは購入に至りにくい現実が浮き彫りになっています。
この結果から、中小企業がインフルエンサーマーケティングを行う際には、扱う商材の価格帯や特性によって、期待できる効果やKPI設定を変える必要があることが分かります。
逆効果も?Z世代が悪印象を抱く案件動画とは
さらに注目すべきは、案件動画が必ずしもポジティブな印象を与えるとは限らないという点です。特に「脱毛、歯列矯正、美容施術、整形など」のジャンルでは、案件動画に対する印象が悪い傾向が見られました。
これらのジャンルの案件動画について、「どちらかというと悪印象」「悪印象」と回答したZ世代は48%にのぼり、「好印象」「どちらかというと好印象」と回答したのはわずか9%でした。これは、他のジャンル(コスメ、スキンケア、食品、衣服)と比較して悪印象の割合が20%以上も高い結果です。
なぜ、これらのジャンルの案件動画は悪印象を持たれやすいのでしょうか?自由回答からは、以下のようなZ世代のリアルな声が挙がっています。
- 「少し胡散臭く感じる」
- 「知らない人が案件ということを黙って褒め続けている」
- 「どのインフルエンサーも自分が施術を受けたように見せて、同じ動画を使っていた」
これらの意見から、情報の透明性の欠如や、過度な演出・宣伝文句、インフルエンサー自身の体験に基づかないような表面的な紹介などが、Z世代の不信感を招いていると考えられます。特に、実際の使用感が映像でリアルに見えづらく、かつ高額な「脱毛、歯列矯正、美容施術、整形など」は、視聴者がより懐疑的になりやすいと言えるでしょう。
この結果は、中小企業がインフルエンサーマーケティングを実施する上でヒントになります。つまり、インフルエンサー選定や動画コンテンツの企画において、「信頼性」や「誠実さ」を欠いたアプローチは、かえってブランドイメージを損なうリスクがあるということです。
Z世代の心を掴む!信頼されるインフルエンサーと案件動画の法則
では、Z世代から信頼され、実際に購買行動にも繋がりやすい案件動画とはどのようなものなのでしょうか。また、どのようなインフルエンサーが支持されているのでしょうか。調査結果から、その「法則を探ります。
「正直さ」が鍵!好印象な案件動画の4つの共通点
今回の調査から、Z世代が好印象を抱く案件動画には、大きく分けて以下の4つのポイントが見られました。
- 良いところだけでなく、悪いところも説明している: メリットばかりを強調するのではなく、デメリットや注意点にも触れることで、情報の客観性と信頼性が増します。
- 案件であるとはっきり述べている: 「これは企業からの依頼案件です」と正直に伝えることで、透明性が担保され、かえって視聴者からの信頼を得やすくなります。ステルスマーケティング(ステマ)と疑われるような曖昧な態度は逆効果です。
- 案件っぽくない(自然である): 過度な演出や台本感が強いものではなく、インフルエンサーが普段の投稿と同じような自然体で商品やサービスを紹介している動画は、好意的に受け止められやすい傾向があります。
- 実際に普段から使用している: インフルエンサーがその商品を本当に愛用しており、日常的に使っている様子が伝わると、紹介内容に説得力が増し、共感を呼びやすくなります。
これらのポイントから、「誠実さ」と「リアルさ」がZ世代に響く案件動画の重要な要素であると言えます。企業側も、インフルエンサーに対してこれらの点を理解してもらい、正直な感想を発信してもらうことが成功の鍵となります。
Z世代が本当に信頼するインフルエンサーとは?
次に、Z世代が案件動画において信頼を置いているインフルエンサーの理由が下記になります。
- 「来る案件全て受ける訳ではない」「マイナスなところも発信してくれる」
- → 本当に良いと思ったものだけを紹介し、正直な意見を述べる姿勢が信頼に繋がっている。
- 「真面目で誠実だから」「登録者数が多いから」
- → 長年の活動で培われた誠実な人柄と、圧倒的なチャンネル登録者数が信頼の基盤となる。
- 化粧品に対する知識や研究心が高く、好感度が高い。
- → 専門性と探求心、そしてそれに基づく質の高い情報発信が評価される。
これらの結果から、Z世代が信頼するインフルエンサーには、以下のような共通点が見られます。
- 情報の選別: 何でもかんでもPR案件を受けるのではなく、自身が良いと思ったものを選んでいる。
- 正直なレビュー: メリットだけでなく、デメリットや改善点も正直に伝える。
- 誠実な人柄: 長期的な活動の中で、視聴者との信頼関係を築いている。
- 専門性: 特定の分野において深い知識や経験を持っている。
中小企業がインフルエンサーを選定する際には、単にフォロワー数が多いだけでなく、そのインフルエンサーが持つ「信頼性」や「専門性」、そして自社のブランドや商品との「親和性」を慎重に見極める必要があります。
中小企業がインフルエンサーマーケティングを成功させるための3つのポイント
これまでの調査結果を踏まえ、中小企業がZ世代に向けたインフルエンサーマーケティングを成功させるために押さえておくべき重要なポイントを3つにまとめました。
- 目的とターゲットの明確化: まず、「誰に(どんなZ世代に)」「何を伝え(どんな行動を促し)」「何のために(売上向上、認知度向上など)」インフルエンサーマーケティングを行うのかを明確にしましょう。目的が曖昧なままでは、適切なインフルエンサー選定も、効果測定もできません。
- インフルエンサー選定の重要性: フォロワー数や知名度だけでインフルエンサーを選んではいけません。自社の商材やブランドイメージと親和性が高く、ターゲットとするZ世代から本当に信頼されているか、エンゲージメント率(いいね!やコメントなどの反応率)は高いかなどを多角的に評価しましょう。マイクロインフルエンサー(フォロワー数が比較的少ないが、特定分野で強い影響力を持つ人)の起用も有効な場合があります。
- 「誠実さ」と「透明性」を持った情報発信: Z世代は「作られた情報」に敏感です。インフルエンサーには、実際に商品やサービスを試してもらい、彼ら自身の言葉で正直な感想を発信してもらうことが何よりも重要です。企業側が過度な指示を出したり、良いことばかりを言わせようとしたりするのは避けましょう。また、必ず案件であることを明示(#PR、#提供など)し、透明性を確保することが、炎上リスクを避け、長期的な信頼関係を築く上で不可欠です。
中小企業がインフルエンサーマーケティングで注意すべき落とし穴
Z世代への効果的なアプローチとなり得るインフルエンサーマーケティングですが、実施する際にはいくつかの注意点も存在します。思わぬ落とし穴にはまらないために、以下の点を理解しておきましょう。
- ステルスマーケティング(ステマ)のリスクと法規制: 2023年10月から、日本でも景品表示法においてステルスマーケティングが規制対象となりました。企業がインフルエンサーに依頼して商品やサービスを宣伝させる場合、それが広告であることを消費者に隠していると、法的な問題に発展する可能性があります。必ず「PR」「広告」「〇〇社提供」などの表示を行い、透明性を確保しましょう。
- 炎上リスクとその対策: インフルエンサーの過去の発言や行動、あるいはPR投稿の内容が不適切であった場合、企業のブランドイメージを大きく損なう「炎上」に繋がる可能性があります。インフルエンサー選定時には、過去の投稿内容や評判などを十分に調査することが重要です。また、万が一炎上が発生した場合の対応フローを事前に準備しておくこともリスクマネジメントの一環です。
- 費用対効果の見極め方: インフルエンサーマーケティングには一定の費用がかかります。「フォロワー単価〇円」といった単純な計算だけでなく、期待する成果(売上、ウェブサイトへのアクセス数、問い合わせ数など)に対するKPIを設定し、施策実施後に効果を測定・分析することが重要です。効果が見えにくい場合は、インフルエンサーの選定や依頼内容、情報発信の方法を見直す必要があります。
まとめ
今回の「サークルアップ」によるZ世代の案件動画に対する意識調査は、中小企業経営者の皆様にとって、今後のマーケティング戦略を考える上で多くのヒントを与えてくれたのではないでしょうか。
Z世代にとって、インフルエンサーの「案件動画」は当たり前の情報源ですが、彼らはその情報を鵜呑みにするのではなく、シビアな目で評価しています。特に、「誠実さ」「リアルさ」「透明性」が欠如した情報発信は、かえって悪印象を与え、企業のブランド価値を損なうリスクすらあります。
一方で、Z世代の心を掴むインフルエンサーは、良い点も悪い点も正直に伝え、案件であることを明示し、普段からその商品を愛用しているような自然体で情報を発信しています。
中小企業がZ世代に効果的にアプローチするためには、
- 自社の目的とターゲットを明確にする
- フォロワー数だけでなく、信頼性や親和性を重視してインフルエンサーを選定する
- インフルエンサーには正直な情報発信を依頼し、透明性を確保する
といったポイントを押さえることが極めて重要です。
情報過多の時代だからこそ、Z世代は「信頼できる情報」と「共感できる発信者」を求めています。中小企業ならではのユニークな商品やサービス、そして誠実な企業姿勢は、適切なインフルエンサーとの連携によってZ世代の心に響き、未来の優良顧客獲得へと繋がるかもしれません。

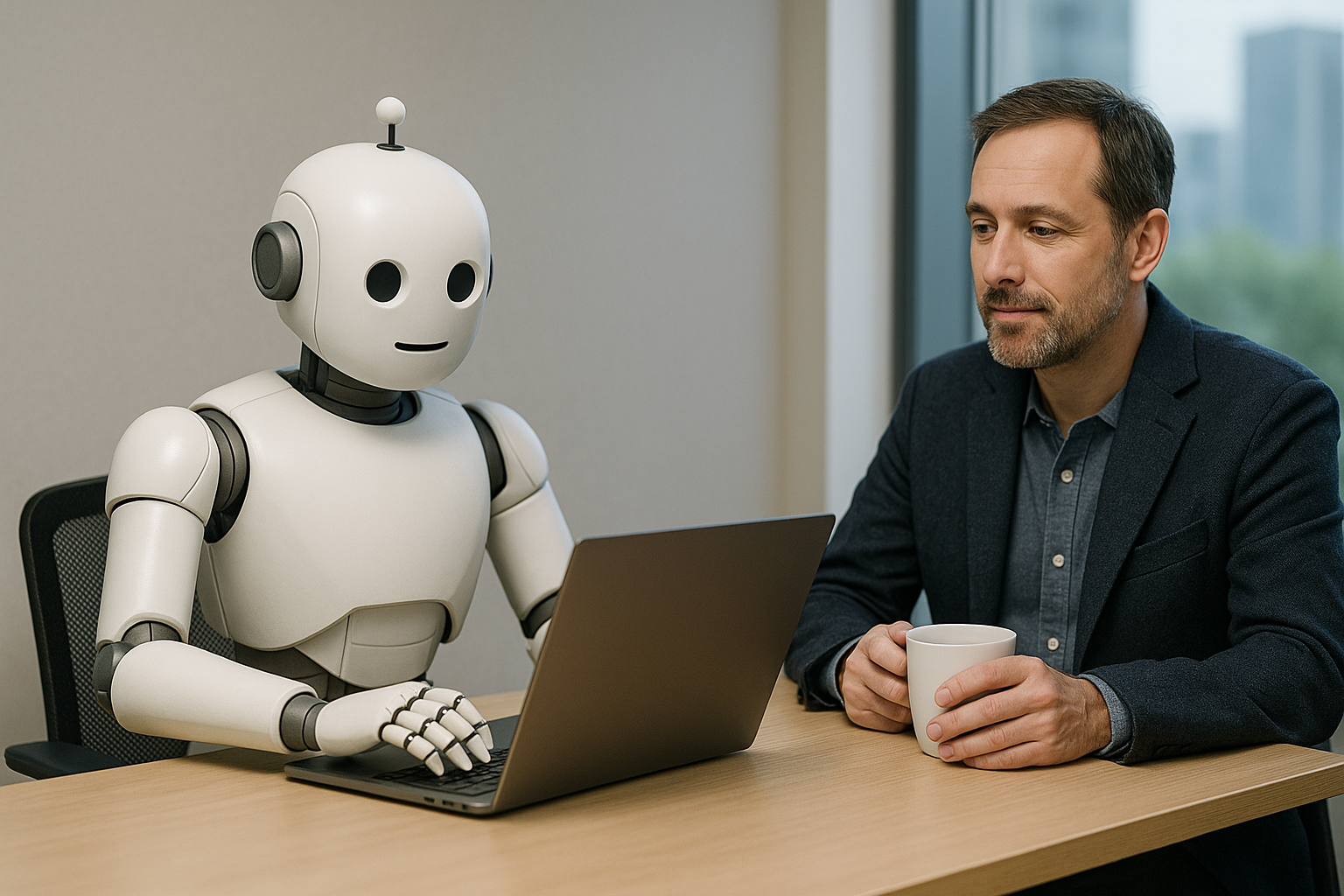
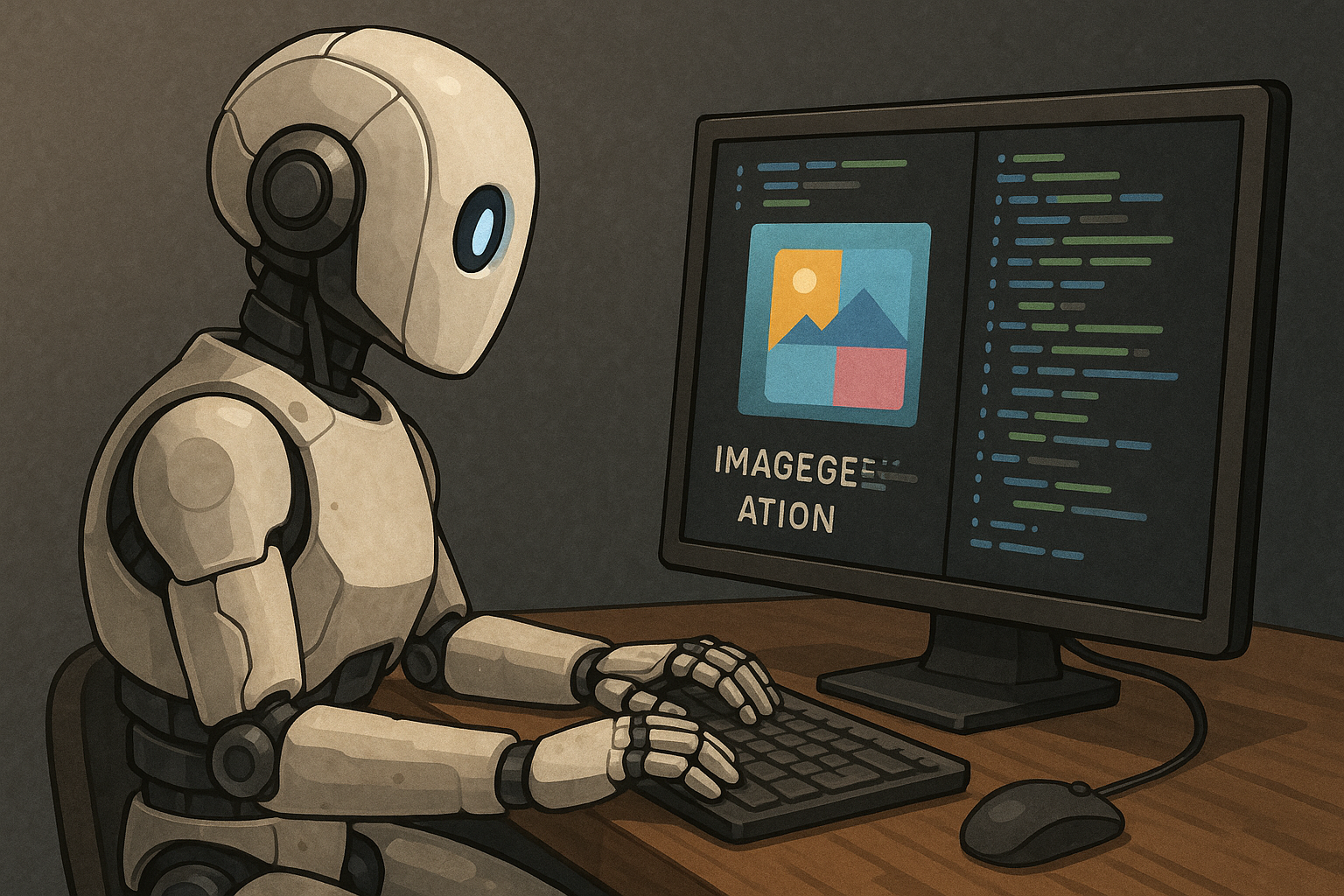
コメント